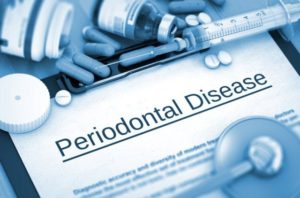歯周病と全身疾患(糖尿病をはじめとする生活習慣病)
歯周病と全身疾患について
1960年代になり歯周病の原因がプラークであることが証明され、1990年代にはそれらの研究を踏まえ、歯周病と全身の健康状態が密接に関連し合っている事を示唆するエビデンスが蓄積されはじめ、歯周病と全身疾患との相互関係の解明を目的とした歯周医学が発展してきています。
ここでは、最近よくトピックスとして取り上げられる歯周病といくつかの疾患の関連性を書いてみたいと思います。
名古屋市の検診
名古屋市では歯周疾患でお困りの方が多い事から検診を行うようになっています。糖尿病などの疾患が一般的になりつつある中で、まだ歯周病の怖さが一般的にはなっていないような気がしています。
ごきそ歯科があります昭和区でもまだまだ情報が足りていないのか歯周病に関して正しい情報をお持ちでない方が多いようです。
このカテゴリーでは発信源としては小さいですが、歯科医院レベルで歯周病と全身疾患の様々な情報を発信していきたいと考えています。